前回のブログでは
足部の筋肉や靭帯、アーチのことや
足、爪のトラブルについて書きました。

今回は、爪の構造や爪の正しい切り方、フットケアの方法を書きたいと思います
coolbearです。
もくじ
- 爪の構造と役割
- 爪の正しい切り方とおすすめの爪切り
- フットケアの重要性
- フットケアの方法
- 正しい靴の選びかた
- 足の運動
- まとめ
爪の構造
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_hada-college/hcp/learn/dermatology/nail/ より引用
普段“爪”と呼んでいる目に見える部位は“爪甲”(そうこう)という部位です。
この爪甲と皮膚の中に隠れている周辺組織、爪根(そうこん)、爪母(そうぼ)、爪床(そうしょう)、爪下皮(そうかひ)から成り立っています。
爪は爪母で成長し、手の爪は1日約0.1mm、足の爪はその半分で0.05mm成長すると言われているが、季節や爪の状態でも変わってきます。
爪は硬いためカルシウムでできていると思われがちですが、タコが皮膚を守ろうとして
皮膚の成分である硬い蛋白質のケラチンという組織に変わり厚くなったものと似ている。
人間の進化の過程で指先を守るためにタコが爪に変わっていったと考えられている。
皮膚は軟ケラチン、爪や毛髪は硬ケラチンからできているため硬さが異なっている。
爪が頑丈な理由として、3層構造になっており、上、下層では繊維が縦に走り、中間層では横に走って重なり合っており、
まるで合板のような構造になっているからである。
爪の役割は手足の指の先端を保護し、
触感を敏感にさせて手足の指の力を増加させる機能があり
足指の爪は足の先端にかかる負担のバランスをとっているので2本足で歩行がスムーズにできます。
手の爪は小さなものをつまむ時の助けとなります。
なので爪が何らかの原因でなくなると、きっと不便を感じることでしょう。
爪の正しい切り方
爪は「スクエアオフ」に切るのが良いとされています。
上の図を参考にしてみてください。
まずはフリーエッジを1mm残しまっすぐに切ります。
両端の角を20°〜30°の角度をつけて切る
切り口を滑らかにしてスクエアオフの形にする。
おすすめの爪切り
私はフットケアサロンに通っていたこともあり
ニッパー型の爪切りがとても使いやすく
今でも愛用しています。
中でも少し値段は張りますが
のニッパーが使いやすくて好きです。
好きすぎて、新潟まで出向いたくらいです。
職人さんがひとつひとつ手作りしてくれて
買った爪切りの研ぎ直し(有料)もしてくれるので
ずっと使うことができます。
本当におすすめです。
ただニッパー型の爪切りは自分というよりは
他の人から切ってもらうことに使用するには
かなりいい爪切りなのですが、
自分の爪をニッパーで切るのは少しコツがいるかもしれません。
そこで他にもおすすめなのは貝印さんの直線刃の爪切りです。
巻き爪などのトラブルがある方には
とってもおすすめです。
丸型ではなく直線というのがポイントです。
丸型は巻き爪の角の部分に歯を入れることが
難しいのですが直線刃は比較的入れやすいし切り過ぎを予防できます。
フットケアの重要性
足の爪は先に述べた通り、爪先にかかるかかる負担を瞬時に判断して
爪先に力が入り蹴り上げて前に足を出すのに重要な役割をしています。
アーチが崩れ開帳足になったり、外反母趾、
ハンマートウなどの足の変形が起きたり
爪の肥厚や爪の間違った切り方うをしたり、
足に合わない靴の影響でトラブルが起きたりします。
その影響で長い年月をかけて生活能力の低下をきたしたり、
バランスの悪い歩き方をすると
膝痛や腰痛の原因にもなります。
なので足の観察をして、異常の早期発見と、早期対応、適切なケアをして
悪化を予防するのは大切です。
足を守ることは健康寿命の延伸や介護予防にも直結してきます。
人生100年の時代、これからますますフットケアの重要性は高まると思います。
フットケアの方法
フットケアと言ってもどんなことをするのでしょうか??
健康維持、病気の予防、病気の悪化予防など足のケアを行うことで
血流の正常化、神経への刺激を通してその人の生活をより良い方向へ向かうことが
一番の目標です。
- フットマッサージ
オイルを使うことが重要です。
力を入れずに、足先から太ももに向かって優しくなぞっていきます。
これを何回か繰り返すだけでも効果があります
お風呂上がりが、血管も拡張しているので
効果が大きくなりますが
足湯に浸かることも同様の効果ありますので
時間がない時はおすすめです。
心臓から押し出された血液は全身にまわりまた心臓に戻ってきます。
血液が心臓に戻るためには全身の筋肉がそのポンプ役として活躍します。
心臓から下にある静脈は引力に逆らって心臓に戻らなければなりません。
なので下の静脈は逆流防止のための弁があることに加え、筋肉が動くことにより
心臓に戻っていきます。
現代の人は車社会に加え足を使うことが少なくなることにより
このポンプ作用が弱まっています。
それを手助けすることにマッサージがあります。
効果としては
血行促進
内蔵・器官の機能正常化
ホルモンバランスの調整が挙げられます。
マッサージオイルは自分が好きなもので構いませんが
ラベンダーには殺菌作用、鎮痛鎮静作用、抗炎症、癒傷作用
テイートリーには抗真菌作用、抗菌、ウイルス作用、免疫促進作用、去痰作用
レモンには殺菌、抗バクテリア作用、収れん作用、胆汁促進作用があります
体調によって使い分けるのもいいかもしれません。
ベビーオイルもおすすめです。
敏感肌の方のは刺激が少ない方がいいかもしれません。
正しい靴の選び方
足にフィットしてしないと靴擦れを起こしたり、血管を圧迫してしたりする。
また蒸れやすい材質だと水虫ができやすくなる。
足の病気の予防にとって靴選びは大切です。
1、靴の選び方
足にフィットして、爪先を動かしても当たらないもの(計測してから買うのがベスト)
自分の足がどんな形なのかを知って足にあった靴を選びましょう。(スクエア型、エジプト型、ギリシャ型か)
ハイヒールなどで、一ヶ所に体重がかかるものは避ける
靴底にクッションがあるウオーキングタイプの靴が良い
靴を買うときは夕方にサイズを合わせて選ぶ
新しい靴は、最初から長時間は履かずに徐々に慣らす
2、靴の履き方
椅子に座り、靴を履き、踵に当ててトントンとしてから、紐をしっかりと結ぶ
おすすめ!足の運動をしましょう。
- タオルギャザー:タオルを床に敷き、裸足で踵を上げないで指先を使いタオルを掴んで自分方に引き寄せます。20−30回程度

- ボールペン掴み:床に落ちているボールペンを足の指でつまむ
- 太ももの内側を鍛える:椅子に座り太ももにボールを挟み、5秒キープします。朝夕に20回ずつ

- 床に座って片足を上げ下げする:片足を伸ばし床から10cm上げ、5秒キープしてから下げる
足のストレッチ(おまけ)
- 足首回し:椅子に座り、片足の太ももに反対の足首をかけて、手で足首を回す(両足20回)

- 手と足で「握手」する体操:足の小指と薬指の間に、手の小指を入れる。順番に薬指から親指まで入れて、手と足の指を組み合わせる。きちんと握れたらゆっくり足首を回す。(両足20回)慣れるまでは痛いかもしれませんが、回数を重ねていくうちにできるようになります。

- 足指ジャンケン:下の図のように足でジャンケンをする動きをします。慣れない人は、最初は足がつるような感じがあるかもしれません、その場合は無理をせずに休みましょう。

まとめ
介護予防としても、今後必要性が高まると思われるフットケア。
まずは自分の足のことを理解し、足のケアや運動を日常に取り入れ、
靴などの見直しをすることで、健康寿命を伸ばすことができます。
毎日少しずつでも継続して、自分の足を好きになりましょう。
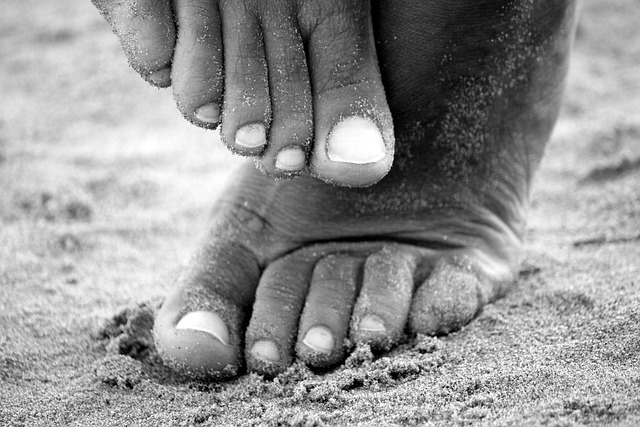



コメント